児童扶養手当
最終更新日:2025年12月2日
ページID:000003609
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
対象外となるケース
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
- 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
「生計を同じくする」とは
児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
1 法律上の婚姻関係にあること
2 住民票上同一住所地にあること
3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
1 法律上の婚姻関係にあること
2 住民票上同一住所地にあること
3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
所得制限
請求者及び扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)の令和6年中の所得が下表の限度額以上のときは、手当の全部(または一部)は支給されません。
この限度額表は、令和7年10月から令和8年9月までの請求時に適用されます。
この限度額表は、令和7年10月から令和8年9月までの請求時に適用されます。
| 扶養親族数 | 本人(請求者) 全部支給 |
本人(請求者) 一部支給 |
配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人増 | 380,000円の加算となります | 380,000円の加算となります | 380,000円の加算となります |
- 扶養親族数・・・令和6年中の所得の申告時に申告した扶養親族の人数
- 所得額・・・令和6年中の年間収入 -(給与所得控除または必要経費)- 控除額(下記ファイル参照)
- 児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等につき、その80%を養育費として所得に含めます。
- 本人若しくは対象児童が公的年金を受給している場合は、支給制限があります。障害基礎年金等を受給している方の受給の範囲や認定のための所得の範囲は、こちら【PDF形式:525KB】をご確認ください。
扶養義務者とは
受給者と同じ住所に同居している直系血族および兄弟姉妹です。
たとえば、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えた子などです。18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります。詳しくは、担当にお問合せください。
【扶養義務者の範囲】下記の図の、受給権者から見て、濃く塗ってある部分を扶養義務者として判定します。
たとえば、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えた子などです。18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります。詳しくは、担当にお問合せください。
【扶養義務者の範囲】下記の図の、受給権者から見て、濃く塗ってある部分を扶養義務者として判定します。
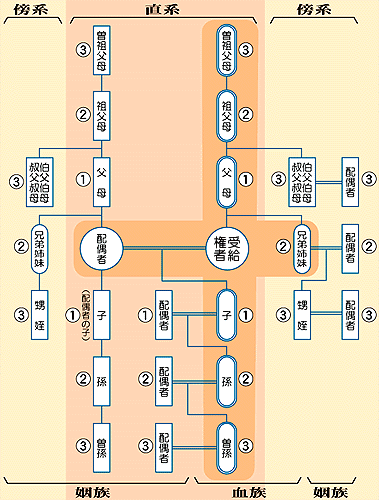
手当月額
手当月額は所得によって変わります。
| 本体額 | 全部支給 | 46,690円 |
| 一部支給 | 46,680円~11,010円 | |
| 第2子以降加算額 | 全部支給 | 11,030円 |
| 一部支給 | 11,020円~ 5,520円 |
- 本人若しくは対象児童が公的年金を受給している場合は、手当の計算方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。
一部支給の月額計算方法
(税法上の扶養親族が1人の場合/10円未満は四捨五入)
手当月額=46,680円-(あなたの所得額-1,070,000円)×0.0256619
第2子以降加算額=11,020円-(あなたの所得額-1,070,000円)×0.0039568
手当月額=46,680円-(あなたの所得額-1,070,000円)×0.0256619
第2子以降加算額=11,020円-(あなたの所得額-1,070,000円)×0.0039568
- 扶養親族数が0人の場合は、上記の式の 「1,070,000円」 の部分に 「690,000円」 を、扶養親族数が2人の場合は、 「1,450,000円」 を、扶養親族数が3人の場合は、 「1,830,000円」 を入れて計算します。
支払期間と支払月
支払期間
児童扶養手当は、認定請求のあった日の属する月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
支払月
1月(11,12月分)、3月(1,2月分)、5月(3,4月分)、7月(5,6月分)、9月(7,8月分)、11月(9,10月分)の各10日頃、指定の口座へ振り込みます。
なお、令和7年度は5月12日(月)、7月10日(木)、9月10日(水)、11月10日(月)、1月13日(火)、3月10日(火)に振り込み予定です。
なお、令和7年度は5月12日(月)、7月10日(木)、9月10日(水)、11月10日(月)、1月13日(火)、3月10日(火)に振り込み予定です。
認定請求
受給資格のある方は、下記書類を持参して児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)でお手続きしてください。
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(請求者、支給対象児童、扶養義務者等のもの)
- 例 マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票等
- 請求者の本人確認書類(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。)
- 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
- 書類B 加入している健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書)、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等
- 請求者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
- 都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。
- その他
- 父または母もしくは児童が障害を有するときは、障害認定診断書が必要となります。なお、障害の程度によっては障害者手帳等で診断書に代えることができます。詳しくはお問い合わせください。
- 請求者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。
- マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い戸籍謄本や課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能になりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類を提出いただくことがあります。
- 戸籍謄本等の提出省略をした場合、通常より審査に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
- 外国籍の方は「該当事由の分かる公的書類」及び「現在独身であることの分かる公的証明」をご用意ください。
- 所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となります。
- 証明書類は発行日より1ヵ月以内のものに限ります。
現況届
毎年11月~翌年10月までをもって、1事業年度となっています。
児童扶養手当の受給資格がある方は、毎年8月に「現況届」を提出することとなっています。この現況届は、所得状況・養育状況等を確認し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
また、手当の受給開始から5年を経過する等の要件にあてはまる受給者について、5年を経過する等した月の翌月分以降の手当額の2分の1が支給停止されます。ただし、就労等自立を図るための活動をしている、又は就労困難な事情(障害、病気、親族の介護等)がある場合には、対象となる年の6月頃に送付される届出書類を提出することにより、手当額の2分の1の支給停止の適用が除外されます。
児童扶養手当の受給資格がある方は、毎年8月に「現況届」を提出することとなっています。この現況届は、所得状況・養育状況等を確認し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
また、手当の受給開始から5年を経過する等の要件にあてはまる受給者について、5年を経過する等した月の翌月分以降の手当額の2分の1が支給停止されます。ただし、就労等自立を図るための活動をしている、又は就労困難な事情(障害、病気、親族の介護等)がある場合には、対象となる年の6月頃に送付される届出書類を提出することにより、手当額の2分の1の支給停止の適用が除外されます。
その他の手続き
資格喪失の届出
次の場合は、手続きが必要です。担当までお問い合わせください。
- 受給者である父または母が婚姻(事実婚も含む)したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
変更の届出
次の場合等は、手続きが必要です。必ず届け出てください。
- 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 住所・氏名を変更したとき
- 手当の振込先金融機関を変更したいとき(受給者本人名義に限ります)
【必要書類】
- 変更届【PDF形式:47KB】(A4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。)
- (氏名を変更したときは)氏名変更があった者の戸籍謄(抄)本
- (児童が別居したときは)児童の属する世帯全員の住民票(調査書も必要となります。詳しくはお問い合わせください。)
- (手当の振込先金融機関を変更したいときは)変更後の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
- 受給者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。
【届出方法】
- 児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での届出
- 郵送での届出
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
受給証明
手当を受給していることの証明が必要となったときは、受給証明の発行を申請してください。
なお、児童扶養手当証書がお手元にある場合、受給証明の発行は原則行いません。
【必要書類】
【申請方法】
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
なお、児童扶養手当証書がお手元にある場合、受給証明の発行は原則行いません。
【必要書類】
- 児童扶養手当受給証明願【PDF形式:65KB】(A4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。)
- 受給者の本人確認書類
【申請方法】
- 児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での届出
- 郵送での届出
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
証書の再交付
児童扶養手当証書を紛失したときは亡失届により再交付申請をしてください。
【必要書類】
【申請方法】
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
【必要書類】
- 児童扶養手当証書亡失届【PDF形式:249KB】(A4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。)
- 受給者の本人確認書類
【申請方法】
- 児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での届出
- 郵送での届出
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
その他のひとり親家庭向け経済支援について
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。
