自立支援医療(精神通院医療)
最終更新日:2025年11月4日
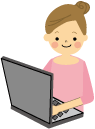
必要書類等
申請に必要な書類
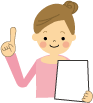
申請書にご記入いただいた電話番号にご連絡させていただく場合があります。
※ 指定医療機関の医師が記載した日から3か月以内のものが必要です。
※ 診断書作成料金は、自立支援医療費の支給対象外です。
※ 診断書の添付が不要となる場合があります。
[例]●受給者証有効期間内の更新申請で、前回の申請で診断書を添付した場合
●有効期限内の手帳をお持ちの方が、自立支援医療(精神通院医療)の新規申請(再開申請を含む)を
行う場合(診断書によらず手帳の写しで申請することができます。)
ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、意見書の添付が必要です。
※診断書の提出は2年に1回ですが、更新申請の手続は毎年必要です。
詳しくは、担当保健センターにお問い合わせください。
以下の確認書類のいずれかをご持参ください。
□マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの
⇒ 画面印刷は、ご家庭やコンビニエンスストアのプリンター(スマートフォン対応)で可能です。
□資格証明書
□資格情報のお知らせ
□従来の保険証(有効期限内のもの/有効期限の記載のないものは令和7年12月1日まで)
※受給者と同一「世帯」全員分の確認書類が必要です。
○「社会保険・本人」…本人の確認書類が必要です。
○「社会保険・家族」…受診者本人と被保険者両方の確認書類が必要です。
ただし、受診者本人の確認書類で被保険者の氏名が確認できれば、
本人分のみで結構です。
○「国民健康保険」 …同じ国民健康保険に加入している世帯全員分の確認書類が必要です。
(国民健康保険組合に加入の方も同様です。)
※「高齢受給者証」をお持ちの方は、併せてお持ちください。
○「後期高齢者医療制度」… 後期高齢者医療に加入している世帯全員分の確認書類が必要です。
マイナンバーを利用した自治体間の情報連携により、必要書類の一部が省略できます。
なお、区市町村民税が未申告の方は事前に申告が必要です。
申請の際は、個人番号が分かる以下の書類のいずれかをご持参ください。
□個人番号(マイナンバー)カード
□個人番号通知カード
□個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、所得税源泉徴収書など
※加入されている健康保険によって、ご家族の個人番号(マイナンバー)も必要になる場合があります。
※申請者ご本人様確認のため、運転免許証等の写真付の公的証明書をご持参ください。
お持ちでない場合は、事前に保健センターにお問い合わせください。
★省略できる提出書類
○ 区市町村民税課税(非課税)証明書および税額決定通知書
・新宿区で住民税が課税されている場合には、公簿により確認をしますので、
申請書の所定欄に新宿区が保有する情報を確認するための同意署名をお願いします。
・新宿区で住民税が課税されていない場合には、個人番号(マイナンバー)を利用した
情報連携により確認をしますので、申請書の所定欄に新宿区等が保有する情報を
確認するための同意署名をお願いします。
○生活保護受給証明書(生活保護受給中の方)
○健康保険の情報が確認できる書類
※個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携は、場合によっては申請日当日に照会が完了しないため、
受付を保留にさせていただくことがあります。
また、上記書類の省略ができない場合もありますので、ご了承ください。
詳しくは、担当保健センターにお問い合わせください。
5 受給者証原本 (更新申請の場合)
新しい受給者証が交付されるまでの間の受診については、申請時にお渡しする受給者証のコピーと
申請書控を医療機関・薬局に提示してください。
□マイナンバー(個人番号)通知カード
□マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、所得税源泉徴収書など
・申請者ご本人の確認のための書類
□精神障害者保健福祉手帳(写真付)、運転免許証等の写真付の公的証明書
□写真付の公的証明書をお持ちでない場合は、保健センターにお問い合わせください。
区市町村民税が非課税世帯の方へ
- 国民健康保険の精神通院医療費助成制度(都内区市町村国保の方)
※ 組合国保・都外の市町村国保は対象外のため、自己負担額については、 各国保組合・国保担当課等にお問い合わせください。
- 社会保険、後期高齢者医療制度および国民健康保険組合に加入されている方
申請すると自立支援医療費の自己負担額を東京都が助成。(原則、自己負担額がなくなります。)
所定の欄への○印の記載が必要となりますので、申請書を提出する際、お申し出ください。
- ≪東京都≫自立支援医療(精神通院医療)のページ(新規ウィンドウ表示)自立支援医療(精神通院医療)について詳細が載っている東京都のホームページです。東京都医療費助成制度について、ページの中ほどに掲載されています。
自己負担・有効期間等について
所得の条件【自己負担上限額】
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 〔負担上限額〕 0円 |
| 低所得1 | 区民税非課税世帯で 本人収入80万9000円以下の方(公的年金収入等を含む) |
〔負担上限額〕 2,500円 |
| 低所得2 | 区民税非課税世帯で 本人収入80万9000円を超える方(公的年金収入等を含む) |
〔負担上限額〕 5,000円 |
| 中間所得1 | 区民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯で、 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 ※1 |
〔負担上限額〕 5,000円 |
| 中間所得2 | 区民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯で、 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 ※1 |
〔負担上限額〕 10,000円 |
| 一定所得以上 | 区民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯で、 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 ※2 |
〔負担上限額〕 20,000円 |
※1 「重度かつ継続」非該当の方は、負担上限月額はありません。
自己負担は医療保険の自己負担限度額までとなります。
※2 「重度かつ継続」非該当の方は、この制度は受けられません。
*「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を
「同一世帯」とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
*「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。
<所得区分「一定所得以上」の方へ>
「重度かつ継続」に該当する方を自立支援医療制度の対象とする経過的特例措置は、
令和9年(2027年)3月31日まで延長されました。
有効期間
新規・再開申請の場合、窓口で申請書を受理した日が有効期間開始日となり、1年後の前月末日が有効期間終期となります。
更新を希望する方は、更新の手続を行う必要があります。
更新申請は、有効期間満了日の3か月前から手続ができますので、お早めにお手続ください。
また、更新申請で認定された場合は、現在使用中の受給者証の有効期限終期の翌日から1年後が新たな有効期限となります。
申請先・その他

受給者証交付
変更等の手続
- ≪東京都≫自立支援医療(精神通院医療)のページ(新規ウィンドウ表示)自立支援医療(精神通院)に関しての詳細が載っている東京都のホームページです。
- ≪東京都(中部)≫自立支援医療(精神通院医療)のページ(新規ウィンドウ表示)自立支援医療(精神通院)に関しての案内が載っている東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページです。
