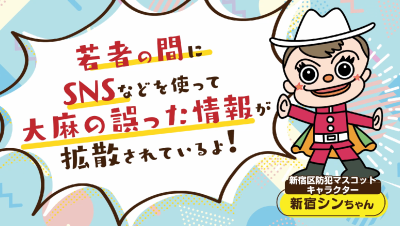ストップ!薬物乱用!
最終更新日:2025年11月13日
ページID:000021299
1 薬物乱用について
(1) 薬物乱用とは
薬物乱用とは、医学的常識を逸脱して依存性の強い薬物を使用することです。たとえ一度の使用でもそれは「乱用」です。またひとたび乱用を始めると、自分の意志ではなかなか止めることができません。
(2) 薬物乱用防止のために
薬物乱用を繰り返すと、薬物依存という「状態」に陥ります。薬物依存の状態になると、身体、特に脳に悪影響を及ぼします。薬物が欲しいという強い欲求、また手の震えや幻覚・意識障害などの離脱症状の苦痛をさけるために、何としてでも薬物を手に入れようという気持ちが抑えられなくなります。更なる犯罪に手を染め、人生を台無しにすることも多くあります。そのようなことにならないために、「1回くらい使っても大丈夫だろう」と安易に手を出さないようにしましょう。また、誘われても勇気をもってはっきりと断りましょう。
また、特に若年層で、医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまう、いわゆる「オーバードーズ」が社会問題化しています。誤った使用方法は、肝臓などの臓器や心を壊してしまうおそれがあるだけでなく、医薬品の乱用から薬物依存を引き起こす可能性もあります。
市販薬を含む医薬品は、「症状に合った薬を、決められた用法・用量を守って正しく使う」ことが最も重要です。
★一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について
(厚生労働省)(新規ウインドウ表示)
★一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(薬剤師、登録販売者の方へ)
(厚生労働省)(新規ウインドウ表示)
また、特に若年層で、医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまう、いわゆる「オーバードーズ」が社会問題化しています。誤った使用方法は、肝臓などの臓器や心を壊してしまうおそれがあるだけでなく、医薬品の乱用から薬物依存を引き起こす可能性もあります。
市販薬を含む医薬品は、「症状に合った薬を、決められた用法・用量を守って正しく使う」ことが最も重要です。
★一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について
(厚生労働省)(新規ウインドウ表示)
★一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(薬剤師、登録販売者の方へ)
(厚生労働省)(新規ウインドウ表示)
(3) 薬物乱用の現状
日本における薬物の生涯経験率は3.4%です。諸外国と比較すると低い値ですが、近年では若年層を中心に大麻による検挙者が急増しています。
大麻事犯の検挙人員は、平成 26 年から増加傾向です。令和6年は 6,078 人と、過去最多となった前年より減少したものの、引き続き高い水準となっています。特に、若年層の大麻乱用が顕著で、30歳未満の割合は年々増加し、令和4年以降は7割を超えています。
また、過去1年以内に市販薬の乱用経験がある高校生は約60~70人に1人の割合であったという調査結果も報告されています。
違法薬物の生涯使用経験率(調査対象年齢:15~64歳、経験率は推定値)
出典:令和5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 薬物乱用・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた大麻等の乱用に関する研究「薬物使用に関する全国住民調査(2023年)」
大麻事犯検挙人員の推移(抜粋)
出典:警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
過去1年以内の市販薬の乱用経験(対象:高校生、経験率は推定値)
出典:令和7年度 厚生労働省依存症に関する調査研究事業「薬物使用と生活に関する全国高校生調査(2024)」
大麻事犯の検挙人員は、平成 26 年から増加傾向です。令和6年は 6,078 人と、過去最多となった前年より減少したものの、引き続き高い水準となっています。特に、若年層の大麻乱用が顕著で、30歳未満の割合は年々増加し、令和4年以降は7割を超えています。
また、過去1年以内に市販薬の乱用経験がある高校生は約60~70人に1人の割合であったという調査結果も報告されています。
違法薬物の生涯使用経験率(調査対象年齢:15~64歳、経験率は推定値)
| 違法薬物の種類 | 経験率(%) |
| 大麻 | 1.5 |
| 有機溶剤 | 1.2 |
| 覚醒剤 | 0.5 |
| MDMA | 0.5 |
| コカイン | 0.4 |
| 危険ドラッグ | 0.3 |
| LSD | 0.3 |
大麻事犯検挙人員の推移(抜粋)
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 検挙人員(人) | 4,321 | 5,034 | 5,482 | 5,342 | 6,482 | 6,078 |
| 検挙人員に対する30歳未満の人数(人) (検挙人員に対する30歳未満の割合(%)) |
2,559 (59.2) |
3,427 (68.1) |
3,817 (69.9) |
3,765 (70.5) |
4,767 (72.9) |
4,478 (73.7) |
| 20~29歳(人) | 1,950 | 2,540 | 2,823 | 2,853 | 3,545 | 3,550 |
| 20歳未満(人) | 609 | 887 | 994 | 912 | 1,222 | 1,128 |
| うち高校生 | 109 | 159 | 186 | 150 | 214 | 206 |
| うち中学生 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 26 |
過去1年以内の市販薬の乱用経験(対象:高校生、経験率は推定値)
| 令和3年 | 令和6年 | |
| いずれかの市販薬乱用 の経験率(%) |
1.6 (62.5人に1人の割合) |
1.4 (71.4人に1人の割合) |
2 啓発活動・相談窓口
(1) 啓発活動

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
厚生労働省、都道府県および(公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、毎年6月20日から7月19日までの1ヶ月間、国民の薬物乱用問題に対する認識を高め、併せて6月26日の「国際麻薬乱用撲滅デー 」の周知を図ることを目的とした街頭キャンペーン等の運動を全国で展開しています。
麻薬・覚せい剤乱用防止運動
厚生労働省では、昭和38年より関係機関の協賛のもと都道府県と一体となって「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を毎年行っており、例年10月1日から11月30日までを運動月間として、国民に対するキャンペーンを行い、麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危険ドラッグ等のおそろしさ、それら乱用による危害についての知識の普及に努めています。
薬物乱用防止ポスター・標語
東京都では、都内の中学生に薬物乱用防止問題について関心を持ってもらうため、ポスター・標語の募集を行っています。新宿区内からも毎年多数の応募があります。
令和7年度は、新宿区内の中学生の標語作品が最優秀賞を受賞しました。
★薬物乱用防止ポスター・標語入賞作品
(東京都)(新規ウインドウ表示)
新宿区の取り組み
新宿区では、東京都薬物乱用防止推進新宿地区協議会と共催で毎年11月に薬物乱用防止街頭キャンペーンを実施しています。
【令和7年度キャンペーン】
日時 11月15日(土)午後2時30分~午後3時30分
場所 JR新宿駅東口
厚生労働省、都道府県および(公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、毎年6月20日から7月19日までの1ヶ月間、国民の薬物乱用問題に対する認識を高め、併せて6月26日の「国際麻薬乱用撲滅デー 」の周知を図ることを目的とした街頭キャンペーン等の運動を全国で展開しています。
麻薬・覚せい剤乱用防止運動
厚生労働省では、昭和38年より関係機関の協賛のもと都道府県と一体となって「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を毎年行っており、例年10月1日から11月30日までを運動月間として、国民に対するキャンペーンを行い、麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危険ドラッグ等のおそろしさ、それら乱用による危害についての知識の普及に努めています。
薬物乱用防止ポスター・標語
東京都では、都内の中学生に薬物乱用防止問題について関心を持ってもらうため、ポスター・標語の募集を行っています。新宿区内からも毎年多数の応募があります。
令和7年度は、新宿区内の中学生の標語作品が最優秀賞を受賞しました。
★薬物乱用防止ポスター・標語入賞作品
(東京都)(新規ウインドウ表示)
新宿区の取り組み
新宿区では、東京都薬物乱用防止推進新宿地区協議会と共催で毎年11月に薬物乱用防止街頭キャンペーンを実施しています。
【令和7年度キャンペーン】
日時 11月15日(土)午後2時30分~午後3時30分
場所 JR新宿駅東口

また、大麻や市販薬の乱用防止のための普及啓発動画を作成し、区内の各大型ビジョンで放映しています。動画の内容は下記「3 普及啓発動画」をご参照ください。
(2) 相談窓口
薬物依存に関するご相談は、住所地を担当する各保健センターまでご連絡ください。
牛込保健センター 03-3260-6231
四谷保健センター 03-3351-5161
東新宿保健センター 03-3200-1026
落合保健センター 03-3952-7161
牛込保健センター 03-3260-6231
四谷保健センター 03-3351-5161
東新宿保健センター 03-3200-1026
落合保健センター 03-3952-7161
4 関連リンク
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。