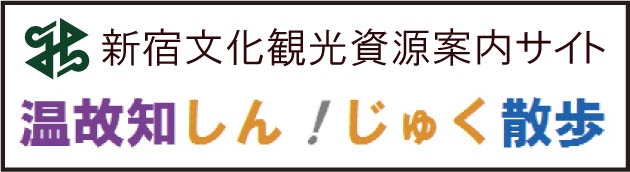新宿区の指定・登録文化財と地域文化財
最終更新日:2025年10月21日
ページID:000008797
 文化財愛護シンボルマーク
文化財愛護シンボルマーク 新宿区は、古くから歴史的環境に恵まれ、地域の歴史や文化を伝える多くの文化財が伝えられています。
新宿区では、これらの貴重な文化財を永く後世に伝えていくため、昭和58年に「文化財保護条例」を制定し、区内の文化財で特に貴重なもの、保存する必要のあるものを区指定文化財・区登録文化財として保護するとともに、ガイドブックや地図での紹介、説明板の設置、一般公開の実施など、周知や活用をはかっています。
また、平成23年4月からは新たに「地域文化財」制度を創設し、明治時代から高度経済成長期に至る近現代の文化財を中心に、保護と活用に努めています。
新宿区では、これらの貴重な文化財を永く後世に伝えていくため、昭和58年に「文化財保護条例」を制定し、区内の文化財で特に貴重なもの、保存する必要のあるものを区指定文化財・区登録文化財として保護するとともに、ガイドブックや地図での紹介、説明板の設置、一般公開の実施など、周知や活用をはかっています。
また、平成23年4月からは新たに「地域文化財」制度を創設し、明治時代から高度経済成長期に至る近現代の文化財を中心に、保護と活用に努めています。
新宿区指定・登録文化財と地域文化財の紹介
- 新宿歴史博物館「所蔵資料検索」(新規ウィンドウ表示)新宿歴史博物館の主な所蔵資料が検索できます。
- 新宿区指定・登録文化財一覧(令和7年9月5日現在) [PDF形式:307KB] (新規ウィンドウ表示)新宿区指定・登録文化財の一覧をご覧いただけます。
- 新宿区地域文化財一覧(令和7年8月15日現在) [PDF形式:2.5MB] (新規ウィンドウ表示)新宿区地域文化財の一覧をご覧いただけます。
新たな新宿区指定文化財
令和7年9月5日付で新宿区指定文化財が2件決定、指定されました。
新宿区指定史跡「栗本丹洲の墓」
種 別:新宿区指定史跡(指定第135号)
所在地:新宿区若葉二丁目3番地 日宗寺
栗本丹洲(くりもと たんしゅう)は、江戸時代後期に活躍した奥医師・本草学者です。宝暦6年(1756)に生まれた丹洲は、実父・田村藍水に本草学を学び、22歳で幕府の奥医師栗本昌友(三代目瑞見)の養子となりました。その後、天明5年(1785)に奥医見習として幕府医官に加えられ、寛政5年(1793)に隠居した父の跡を継ぎ、四代目瑞見を名乗りました。丹洲は、診療のほか、幕府医学館で本草学講義や薬品鑑定に従事し、医学館薬品会では中心人物として度々出品を行いました。また、持ち前の画技を生かして多くの生物図譜を作成しています。なかでも生涯をかけて増補を続けた『千蟲譜(せんちゅうふ)』は日本における初の昆虫図譜であり、その収載数と正確さで高く評価されました。『千蟲譜』は幕末の本草学隆盛に大きな影響を与え、明治以降も広く参照されました。墓所は向かって左に丹洲、右に妻の墓が並び立っています。丹洲の墓石は、総高118.8㎝の安山岩で、戒名「故法印兼薬品鑑定瑞仙院楽我居士」と刻まれています。墓前には「日本医史学会」および「東京名墓顕彰会」が建てた花立てが置かれています。
所在地:新宿区若葉二丁目3番地 日宗寺
栗本丹洲(くりもと たんしゅう)は、江戸時代後期に活躍した奥医師・本草学者です。宝暦6年(1756)に生まれた丹洲は、実父・田村藍水に本草学を学び、22歳で幕府の奥医師栗本昌友(三代目瑞見)の養子となりました。その後、天明5年(1785)に奥医見習として幕府医官に加えられ、寛政5年(1793)に隠居した父の跡を継ぎ、四代目瑞見を名乗りました。丹洲は、診療のほか、幕府医学館で本草学講義や薬品鑑定に従事し、医学館薬品会では中心人物として度々出品を行いました。また、持ち前の画技を生かして多くの生物図譜を作成しています。なかでも生涯をかけて増補を続けた『千蟲譜(せんちゅうふ)』は日本における初の昆虫図譜であり、その収載数と正確さで高く評価されました。『千蟲譜』は幕末の本草学隆盛に大きな影響を与え、明治以降も広く参照されました。墓所は向かって左に丹洲、右に妻の墓が並び立っています。丹洲の墓石は、総高118.8㎝の安山岩で、戒名「故法印兼薬品鑑定瑞仙院楽我居士」と刻まれています。墓前には「日本医史学会」および「東京名墓顕彰会」が建てた花立てが置かれています。
 栗本家墓地
栗本家墓地新宿区指定有形民俗文化財「諏訪神社の絵馬等奉納物」
種 別:新宿区指定有形民俗文化財(指定第136号)
所在地:新宿区高田馬場一丁目12番6号 諏訪神社
旧諏訪村、戸塚村、大久保村を氏子圏とする諏訪神社に伝わった絵馬等奉納物です。総数は61点あり、このうち紀年銘を有するものは寛政6年(1794)の「放鷹の図」を最古として、昭和28年(1953)の棟札類におよびます。
内容は絵馬類53点、棟札類5点、その他3点からなり、このうち絵馬類は諏訪神社関連図5点、社頭祈願図5点、鷹匠関連図7点、歴史・伝説関連図6点、馬を描いた図3点、戦争の図2点、芸能の図2点、花鳥図4点、大久保鉄砲組関連図4点、諏訪神社関連額7点、文芸関連2点、日清・日露戦争関連2点、その他4点からなります。
近世・近代のものが数多くまとまって存在し、寛政7年(1795)の年紀を持つ「諏訪大明神祭礼図」、文政4年(1821)から嘉永2年(1849)にかけて大久保鉄砲組が奉納した4点の「十五間立放奉納額」など、神社や地域の歴史資料として重要なものも含まれます。
全体的に着色の剥落や退色も見られ判読困難なものもありますが、絵画資料、民俗資料のみならず、地域の歴史や信仰、文化を知る上で重要な資料です。
所在地:新宿区高田馬場一丁目12番6号 諏訪神社
旧諏訪村、戸塚村、大久保村を氏子圏とする諏訪神社に伝わった絵馬等奉納物です。総数は61点あり、このうち紀年銘を有するものは寛政6年(1794)の「放鷹の図」を最古として、昭和28年(1953)の棟札類におよびます。
内容は絵馬類53点、棟札類5点、その他3点からなり、このうち絵馬類は諏訪神社関連図5点、社頭祈願図5点、鷹匠関連図7点、歴史・伝説関連図6点、馬を描いた図3点、戦争の図2点、芸能の図2点、花鳥図4点、大久保鉄砲組関連図4点、諏訪神社関連額7点、文芸関連2点、日清・日露戦争関連2点、その他4点からなります。
近世・近代のものが数多くまとまって存在し、寛政7年(1795)の年紀を持つ「諏訪大明神祭礼図」、文政4年(1821)から嘉永2年(1849)にかけて大久保鉄砲組が奉納した4点の「十五間立放奉納額」など、神社や地域の歴史資料として重要なものも含まれます。
全体的に着色の剥落や退色も見られ判読困難なものもありますが、絵画資料、民俗資料のみならず、地域の歴史や信仰、文化を知る上で重要な資料です。
 諏訪大明神祭礼図
諏訪大明神祭礼図新たな新宿区地域文化財
令和7年8月15日付で新宿区地域文化財が2件決定、認定されました。
慶應義塾大学食養研究所跡
種 別:新宿区地域文化財(歴史分野、生活分野)(地域第51号)
所在地:新宿区信濃町35番地 慶應義塾大学病院
食養研究所は大正15年(1926)に、当時の日本の人口・食糧問題の解決や患者の食事療法の研究を目的として慶應義塾大学医学部に設置されました。同年8月には三井財閥の益田孝のほか財界有力者の寄付によって鉄筋コンクリート3階建ての「食養研究所」が建てられました。
ここでは主任の大森憲太を中心に栄養増進、食事療法、ビタミン学の研究が行われ、とくに脚気の原因究明と食事療法において成果をあげました。食養研究所は平成2年(1990)に廃止となり、64年の歴史に幕を閉じます。跡地には往時の食研外壁の一部と平成11年(1999)に設置された「食研跡地記念の碑」が建っています。
所在地:新宿区信濃町35番地 慶應義塾大学病院
食養研究所は大正15年(1926)に、当時の日本の人口・食糧問題の解決や患者の食事療法の研究を目的として慶應義塾大学医学部に設置されました。同年8月には三井財閥の益田孝のほか財界有力者の寄付によって鉄筋コンクリート3階建ての「食養研究所」が建てられました。
ここでは主任の大森憲太を中心に栄養増進、食事療法、ビタミン学の研究が行われ、とくに脚気の原因究明と食事療法において成果をあげました。食養研究所は平成2年(1990)に廃止となり、64年の歴史に幕を閉じます。跡地には往時の食研外壁の一部と平成11年(1999)に設置された「食研跡地記念の碑」が建っています。
 食研跡地記念の碑
食研跡地記念の碑梅屋庄吉旧居跡(エム・パテー大久保撮影所跡)
種 別:新宿区地域文化財(都市・産業分野、文化・芸術分野)(地域第52号)
所在地:新宿区百人町二丁目23番27号 学生の家
日本映画界の草創期に活躍した実業家梅屋庄吉(1868~1934)が、明治42年(1909)から亡くなる昭和9年(1934)まで暮らした旧居跡です。明治39年(1906)に映画会社エム・パテー商会(日活の前身)を設立した梅屋は、同42年に大久保百人町に土地を購入し、自宅とエム・パテー大久保撮影所を建設しました。エム・パテー商会では、海外映画の輸入や映画の自社制作を行い、草創期の日本映画界を牽引しました。また梅屋は、犬養毅をはじめ国内のアジア主義の要人たちとも交流が深く、日本亡命時(1913~1916)の孫文の生活を全面的に支援しました。孫文と宋慶齢の披露宴は梅屋邸で開催されたといいます。梅屋庄吉の東京での活動拠点であったこの地は、日本の文化史上、重要な史跡です。
所在地:新宿区百人町二丁目23番27号 学生の家
日本映画界の草創期に活躍した実業家梅屋庄吉(1868~1934)が、明治42年(1909)から亡くなる昭和9年(1934)まで暮らした旧居跡です。明治39年(1906)に映画会社エム・パテー商会(日活の前身)を設立した梅屋は、同42年に大久保百人町に土地を購入し、自宅とエム・パテー大久保撮影所を建設しました。エム・パテー商会では、海外映画の輸入や映画の自社制作を行い、草創期の日本映画界を牽引しました。また梅屋は、犬養毅をはじめ国内のアジア主義の要人たちとも交流が深く、日本亡命時(1913~1916)の孫文の生活を全面的に支援しました。孫文と宋慶齢の披露宴は梅屋邸で開催されたといいます。梅屋庄吉の東京での活動拠点であったこの地は、日本の文化史上、重要な史跡です。
 梅屋庄吉旧居跡
梅屋庄吉旧居跡本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-文化観光課
電話:03(5273)4126 FAX:03(3209)1500
電話:03(5273)4126 FAX:03(3209)1500
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。